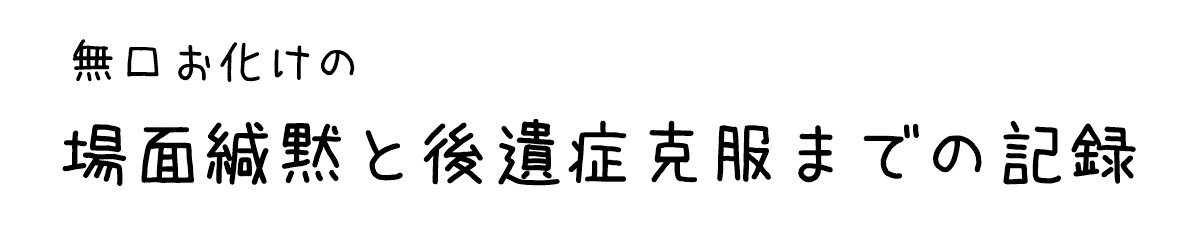場面緘黙の治し方〜周りの協力が得られる人向けの方法
場面緘黙症は高校生ぐらいまで治らない人が多いやっかいな病気です。
でも周りの人たちの協力があれば早期に治すことも可能です。
場面緘黙の治療に有効な方法はスモールステップでしゃべれる場所&人を少しずつ増やしていくことです。

今回は周りの人たちの協力が得られる場合に、場面緘黙を治す効果的な方法を低学年向けのやり方と高学年向けのやり方に分けて考察したいと思います。
低学年向けの場面緘黙の治し方
低学年の場合は主に親が協力します。(先生やカウンセラーでも可)
ちなみに年齢が低ければ低いほど治しやすいです。
①親が学校に行き、遊びながらしゃべる
まずは学校に許可を取り、親が放課後や休日などに学校に行って子どもと遊びます。
で、遊びながらしゃべります。
学校でしゃべることに慣れるためです。
またもし今まであまりやってなかったなら学校の前に公園とか、ゲームセンターとかプールなど、子供向けの施設で一緒に遊ぶことから始めてもいいです。
②①に慣れてきたらそこに仲のいいクラスメイトを加えて遊ぶ(初めはしゃべらなくてもできる遊び)
①に慣れてきたらそこに仲のいいクラスメイトを加えます。
慣れの目安として、場面緘黙の子どもはたいてい家より家の外で遊ぶときの方が緊張する分声が小さくなります。
しゃべるときの声を聞いて、学校でも家でしゃべるときと同じくらいリラックスできてるなと思ったら慣れたと判断できます。
クラスメイトを加えたばかりのタイミングではなかなかしゃべることは難しいので、まずはしゃべらなくてもできる遊びをし、3人で遊ぶことに慣れてください。
親と2人だけの時と同じくらいリラックスできるくらいまで慣れるのが理想です。
しゃべらなくてもできる遊びの例
- トランプ(ババ抜きや神経衰弱など)
- ジェンガ
- オセロ
- 囲碁
- 将棋
など
③②に慣れてきたら言葉を誘発する遊びをしながら自然にしゃべるまで待つ
②に慣れてきたら、時々言葉を誘発する遊びを取り入れてみましょう。
短い言葉を言う遊びが理想です。
例
- トランプ(大富豪、ダウト、ドボン、ブラックジャック、ポーカーなど)
- UNO
- 麻雀
など
慣れてきたらもう少ししゃべることメインの遊びもします。
例
- しりとり
- いっせーのせ(指スマ)
- 山手線ゲーム
- マジカルバナナ
など
親としゃべるときと同じくらいクラスメイトともしゃべれるようになれば成功です。
④③でクラスメイトとしゃべれるようになったら新しいクラスメイトを加えて同じことをする
クラスメイト1人としゃべれるようになったら新しいクラスメイトを加えて同じことをしてください。
新しい子が加わったばかりのタイミングだとしゃべりにくいので最初はなるべくしゃべらなくてもいい遊びをやり、少し慣れてからしゃべる必要のある遊びをやるといいです。
4人になるとできる遊びも増えて盛り上がると思います
4人でやる遊びの例
- トランプゲーム全般
- UNO
- ジェンガ
- 人生ゲーム
- 卓球やバドミントン、バスケなどのスポーツ(体育館が借りれるなら&運動苦手じゃないなら)
など
2:2でチーム戦にするとより盛り上がって楽しくなります。
その際、最初はすでしゃべれる子、または親とチームを組ませて時々チーム同士でしゃべると自然としゃべりやすいです。
⑤しゃべれるクラスメイトを少しずつ増やしていき、教室で自然としゃべれるようになるまで待つ
④までができたらもう成功も同然です。
あとは同じ手順でしゃべれるクラスメイトを増やしていくだけ。
慣れてきたら親なしで子どもとクラスメイトだけで遊ばせてみるのもいいでしょう。
そうやってしゃべれるクラスメイトが増えてくれば、教室で自然としゃべれるようになるのも時間の問題です。
あとは教室でしゃべり出すまで気長に待つだけです。
低学年ならこの手順でかなりの確率で成功してしゃべり始めるはずです。
高学年向けの場面緘黙の治し方
次に高学年向けの方法。
低学年と比べると治療はかなり難しくなりますが、この方法ならそれなりの確率で成功するのではないか、と思います。
①家に仲のいいクラスメイトを招いて遊ぶ(初めはしゃべらなくてもできる遊び)
まずは自宅に1番仲のいいクラスメイトを1人呼んで遊びます。
リラックスして楽しいときが一番しゃべりやすいのでなるべく2人で楽しめる遊びをしましょう。
遊びの例
- 対戦型のテレビゲーム
- 対戦型の携帯ゲーム
- 対戦型のスマホゲーム
- オセロ
- 囲碁
- 将棋
- カードゲーム
など
特にテレビゲームなんかは夢中になって楽しんでるうちに思わずしゃべってしまうかもしれません。
なるべく楽しい遊びをして、自分がしゃべらないことを忘れるくらい夢中になれるとその可能性が高まります。
ただし、この手順は家で友達と遊ぶことに慣れるのが目的なのでまだしゃべれなくてもオッケー。
②①に慣れてきたら言葉を誘発する遊びも時々取り入れて、自然としゃべり出せるまで待つ
自宅でそのクラスメイトと遊ぶことに慣れてきて、そろそろしゃべれそうだなと思ったら、少しだけ声を出す遊びをやりましょう。
いきなり声を出すのが難しければ始めはささやき声でもいいです。
遊びの例
- トランプのスピード、戦争
- ヘッズアップポーカー
など
トランプのスピード、戦争は掛け声を一緒に言うことから始めればしゃべりやすいと思います。
ポーカーは「ベット」「チェック」「コール」「レイズ」など一言言うだけなので比較的しゃべりやすいと思います。
③②でしゃべれるようになったらその人とたくさんしゃべろう
遊びの中でしゃべれるようになったら会話もできるはずです。
慣れてきたら、というかしゃべれたらその日のうちにでも普通にしゃべり始めてしまえると思います。
で、しゃべれるようになったらそれまでしゃべりたくてもしゃべれなかった分話したいことはたくさんあるはずです。
思う存分しゃべって会話を楽しみましょう^^
④③でしゃべれた人と外でも遊んでしゃべる
で、次にその人と家の外でも遊んでしゃべりましょう。
例
- ダーツやビリヤードで遊びながらしゃべる
- 公園でバドミントンをやりながらしゃべる
- スポーツ施設で卓球やテニスなどをやりながらしゃべる
など
まぁ場所はどこでもいいです。
場面緘黙症だと友達と外で遊んだことがほとんどない人が多いと思うので、今まで行きたくても行けなかった場所にどんどん行きましょう。
ファミレスランチでもマックでもカラオケでもボーリングでも。
その人との仲のよさ次第ですが、どこでも自分の行きたいところをたくさん開拓しちゃってください。
⑤④でしゃべれた人と学校の人目のつかない場所で会ってこっそりしゃべる
家の外でもしゃべれたら次は学校です。
まだ人前ではしゃべりにくいと思うのでまずは休み時間や昼休みに2人だけでトイレなど、人目のつかない場所で会ってこっそりしゃべることから始めましょう。
また学校生活でしゃべれないせいで困ったことがあったときなどはその人にこっそり耳打ちでしゃべることもやってみるといいです。
人前じゃ恥ずかしければ最初は廊下とかで。慣れたら教室の目立たないところでも。
⑥同じ手順で学校でしゃべれる人を少しずつ増やしていく
⑤までできるようになったらあとは同じ手順でしゃべれる人を2人、3人と増やしていきます。
1:1の方がしゃべりやすい人、すでにしゃべれるクラスメイトと一緒に3人で遊ぶ方がしゃべりやすい人いると思うので、これはあなたにとってやりやすい方でやればいいです。
⑦しゃべれる人がある程度増えて、学校でしゃべることにも慣れたら時々教室で自然に話しかけてもらい、話せるようになるまで待つ
⑥までしゃべれるクラスメイトが5〜6人にまで増えてきたらそろそろ教室でしゃべれるようになってもいいタイミングです。
その人たちと時々耳打ちでこっそりしゃべってコミュニケーションを取ることは続けつつ、時々普通にしゃべれること前提で自然に話しかけてもらいましょう。
心の準備ができた状態でリラックスできてるタイミングで、しゃべってもしゃべらなくてもいいよスタンスで普通に話しかけられると、しゃべれる可能性が高くなります。
なので自分の中でももうそろそろしゃべれそうだと思ったら、すでにしゃべれる人に頼んで、時々自然に話しかけてもらうようにしてください。
その際はしゃべって答えてもいいし、しゃべらずに答える、または耳打ちでしゃべるのでもいいスタンスでなるべくしゃべらせようというプレッシャーはかけないように注意してもらってください。
以上の緻密なスモールステップを踏めば、高学年でも場面緘黙を今の学校にいるタイミングで治すことは可能だと思います。
基本的には高学年の場面緘黙症は知り合いのいない学校に進学や転向しないと治りにくいです。
特に自力で治す場合は不可能に近いので、今の学校では治らないことを前提に治し方を書いてます。
早くしゃべらなきゃと焦らず、自然と言葉が出るまで気長に待つことが大事
場面緘黙症の治療に焦りは禁物です。
なぜなら、早く治さなきゃと焦って自分にプレッシャーをかけると、緊張するからです。
緊張すればするほど喉の筋肉がこわばり、声が出にくくなります。
だから早くしゃべれるようになりたい気持ちはわかりますが、なるべく自然にしゃべれるまで気長に待つことが大事です。
できるだけリラックスして楽しい気分になれる遊びをしながら自然と口から言葉が出るまで待つのです。
その方が、無理してしゃべろうとするより断然しゃべれるようになる確率は高いと思います。
場面緘黙症は特に高学年であればあるほど治すのは難しいです。
そして高学年の人ほど「しゃべらなければ」というプレッシャーも大きいと思います。
このプレッシャーはしゃべるためには邪魔にしかならないので、「しゃべらなければ」という気持ちはなるべく忘れてください。
そしてここに書いた手順のしゃべらずに遊ぶことを思いっきり楽しんでください。
そうすればきっとしゃべれるはずです。頑張ってください。
関連ページ
- 場面緘黙の治し方〜周りの協力が得られず自力で克服する方法
- 場面緘黙症はあまり知られてない病気なので、周りから理解されず、自力で治すしかない状況にいる人も非常に多いと思います。 私自身もそうでした。 そこで今回は場面緘黙症を自力で治す方法を考察したいと思います。