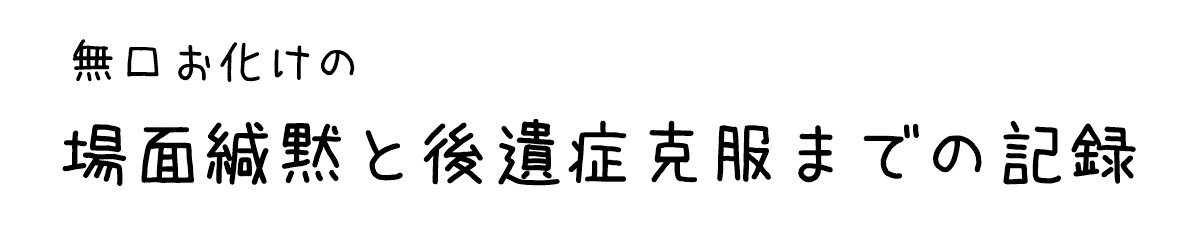【クラスメイト向け】学校でしゃべらない子(=場面緘黙)との接し方

どうも。無口おばけです。
もしもクラスに場面緘黙でしゃべらない子がいたらどう接するべきか?
元場面緘黙だった私がどうしてほしかったか。
この記事ではこれをお伝えしたいと思います。
場面緘黙児がクラスメイトに望むこと
- しゃべらないのではなくしゃべれないということを理解してほしい
- なるべく特別扱いせず普通に接してほしい
- しゃべらないだけで中身は同じだと理解して対等に接してほしい
- しゃべれないせいで困ってるときは察してほしい・助けてほしい
- しゃべってもしゃべらなくてもいいというスタンスでなるべくたくさん話しかけてほしい
1. しゃべらないのではなくしゃべれないということを理解してほしい
まずこれをわかってほしい。
しゃべらないのは自分の意志じゃない。
場面緘黙児だって本当はしゃべりたい。
みんなと同じようにおしゃべりしたい。友達作りたい。
でもそれができなくて毎日つらい思いをしてる。
なのにみんなにはそれがわかってもらえず、ただしゃべれるのにしゃべらない変な奴だと思われてしまう。
だからしゃべらないことを馬鹿にされたり、しゃべることを強要されたりする。

「自分の意志でしゃべらない」んじゃなくて「病気でしゃべれない」ということをわかってほしいです。
まぁ家ではしゃべれるのに学校ではしゃべれないってのは普通の人には理解しがたいことだと思います。
でも本人にもなぜ学校だとしゃべれないかはあまりわかってません。
それが場面緘黙という病気なんです。
場面緘黙症について詳しく知りたい人はこちらの記事を読んでください。
2. しゃべらないだけで中身は同じだと理解して対等に接してほしい
次にしゃべらなくても中身は他の子供と同じだということを理解すること。
で、対等に接すること。
これは人によるんですが、
しゃべらない=普通じゃない=何してもいい、何言ってもいい
と考えちゃう人がいるんですよね。
子どもならまだしも、学校の先生とか親とか、大人にもこういう人はいます。むしろ大人の方が多かった気が…( ゚Д゚)
しゃべらなくても普通の人とまったく同じなんで、ひどいこと言われたら普通に傷つきます。
特に場面緘黙症の子は敏感なので普通の人以上に傷つきます。
また場面緘黙児は感覚が鋭いので言葉自体は悪口じゃなくても声のトーンとか表情とかで馬鹿にしてるのバレバレです。
もし場面緘黙の人と仲良くなりたかったら対等に接してください。
3. なるべく特別扱いせず普通に接してほしい
次に特別扱いせず普通に接すること。
しゃべらないからとか場面緘黙だからって特別扱いされると場面緘黙が治しにくくなります。
またちょっと傷つくかも。
場面緘黙児はしゃべらないからって特別扱いしたり、差別したりすることなく普通に接してくる人が好きです。
またみんなが普通に接してきてくれると「ここでならしゃべってもいいかも」と思えて場面緘黙が治る可能性が少し上がります。
4. しゃべれないせいで困ってるときは察してほしい・助けてほしい
特別扱いしないでほしいというのと若干矛盾するかもしれないですが、困ってる時は察してほしいし、助けが必要な時は助けてほしいです。
なぜなら、しゃべれないと学校生活で何かと不自由があるからです。
例)
- 教科書忘れたけど貸してって言えない
- 授業中トイレ行きたいけどトイレって言えない
- 場面緘黙を知らない人にしゃべるよう強要されて困ってる
- うなずきや首振りなどで答えられない質問をされて困ってる
など
場面緘黙の人は色んな場面でよく困ってます。
困ってる時はたぶん表情に出ます。(無表情の人もいますが)
そういうときに困ってることを察して助けてくれる人がいるとめっちゃありがたいです。
あとしゃべれない子が言いたくても言えないことを代弁してあげたりとか。
助けてくれたらありがとうは言えないけど心の中でめっちゃ感謝してます。
だからもし場面緘黙でしゃべらない子が困ってる様子を見かけたらぜひ助けてあげて欲しいです。
5. しゃべってもしゃべらなくてもいいというスタンスでなるべくたくさん話しかけてほしい
学校でしゃべらない子は始めは不思議に思われて注目されたりもしますが、慣れるとみんなから飽きられて放置されやすいです。
だから友達もできず、教室にいてもいなくても誰も気づかない幽霊のような子どもになりがちです。
場面緘黙の子も孤独だと普通に寂しいです。
中身は普通の子供なので本当はみんなと楽しくおしゃべりしたいし友達も欲しいんです。
でもしゃべれないから誰かが話しかけてくれるのを待ってることしかできません。
「かまってちゃんうざい」みたいに思うかもしれませんがしゃべれないのでどうしようもないんです。
だからなるべく話しかけてあげてほしいです。
そして話しかけるときはなるべく
「しゃべってもしゃべらなくてもいいよ」
というスタンスで話しかけてほしいです。
要は
しゃべることを期待するのでもなく、
絶対しゃべらなくてもいいように気を遣いすぎるのでもなく、
「しゃべってもしゃべらなくてもどっちでもいいよ。気が向いたらしゃべってくれればいいよ。」
という感じで話しかけてくれるのがベストです。
まぁ最初のうちはなるべくYES/NOで答えられる質問中心にした方がコミュニケーションは取りやすいです。
しゃべれなくてもうなづくか首振りはできるので。
でもずっとそればかりだとさすがにつまらないですし、しゃべり始めるきっかけが持てません。
場面緘黙の人も本当はしゃべりたいと思ってますし、その人の心の準備ができていてなおかつ周りの環境がしゃべりやすいものになっていれば、しゃべり始める可能性があります。
で、なおかつしゃべったとしても驚かず、「○○君がしゃべったー!」などと騒がず、今まで通り普通に接すること。
毎日たくさん話しかけられてて、なおかつそれが「しゃべってもしゃべらなくてもいいよ」というスタンスなら、場面緘黙の人のしゃべりたいという気持ちとしゃべってもいいんだという安心感が相まってしゃべり出すことができるのです。
なので場面緘黙の人にしゃべってほしい、仲良くなりたい人はできるだけ毎日そういうスタンスで話しかけ続けてください。
場面緘黙児にしないでほしいこと
次に場面緘黙の子どもにしないでほしいことを言います。
- 「あって言って」と言う
- しゃべらないことを責める
- 無理矢理しゃべらせようとする
- しゃべることを期待する
- しゃべったときに騒ぐ
- しゃべり始めたあとに声の大きさやコミュ障なことをいじる
1. 「あって言って」と言う
しゃべらない子どもに対してよく言ってしまいがちな言葉が「あって言って」
これは言われると困ります。
小学校低学年とかならまぁしょうがないと思いますが、言わないように気を付けてください。
2. しゃべらないことを責める
次にしゃべらないことを責める。
場面緘黙はしゃべらないんじゃなくてしゃべれないので責められてもどうしようもありません。
でも本人は責められると傷つきます。
3. 無理矢理しゃべらせようとする
次に無理やりしゃべらせようとすること。
たぶん場面緘黙の人が一度は経験したことあると思います。
クラスの何人かから囲まれてしゃべるよう強要されたこと。
まぁ本当はしゃべれるのにしゃべらないなら無理矢理しゃべらせればしゃべれるはずだと考えるのは当然だと思います。
でも場面緘黙児本人は
本当はしゃべりたくてしょうがないのにしゃべれない
のです。
だからしゃべれるはずだと思ってしゃべらせようとするのはやめてください。
4. しゃべることを期待する
次にしゃべることを期待すること。
本人はしゃべりたいし周りの子たちもしゃべってほしいと思う気持ちはあるでしょう。
だから場面緘黙の子がしゃべることを期待したくなる気持ちはわかります。
でもその気持ちは抑えて下さい。
場面緘黙児はプレッシャーに弱いんです。
周りからしゃべることを期待されればされるほどしゃべりにくくなります。
あくまで「しゃべってもいいし、しゃべらなくてもいいよ」というスタンスで接してあげてください。
その方が断然しゃべり出す確率が高くなるはずです。
5. しゃべったときに騒ぐ
最後に場面緘黙児が初めてしゃべったとき。
「あ!○○君がしゃべった!」
と騒ぎたくなる気持ちはわかりますが、抑えてください。
騒いだらまたすぐにしゃべれなくなります。
そしたら今までの苦労が水の泡です。
突然しゃべり始めても動揺することなく、まるで今までも普通にしゃべってたかのように接してください。
そしてその日の終わりにでも「しゃべれたね。おめでとう」と言ってあげてください。
みんなで言うんじゃなくて、個別に言う方がいいです。
注目されると緊張してしゃべれなくなっちゃいますからね。
6. しゃべり始めたあとに声の大きさやコミュ障なことをいじる
また場面緘黙でそれまでしゃべらなかった子はしゃべり始めても声が小さかったり、会話がうまくできなかったりすることがあります。
特に学校でしゃべらなかった期間が長ければ長いほどうまくしゃべれない傾向が強いです。
そこで「声ちっちゃい」とか、「もうちょい大きい声出せない?」などと指摘したり、
「聞こえませーん!」などとからかうのは絶対やめてください。
そういうこと言われると自信をなくして余計に声が小さくなりますし、またしゃべれない子供に逆戻りしてしまうかもしれません。
その子にとってはしゃべれるようになっただけでもすごいこと。
そのことをちゃんと認めてあげてください。
声の小ささとか活舌とか、コミュ力不足とかは慣れの問題で解決する問題です。
しかしそれを周りから指摘されたりからかわれたりすると、自信を無くしてずっと声小さいまま&コミュ障なままになってしまいます…。
そうならないよう、声の大きさやコミュ力不足は大目に見て温かい目で見守ってあげてください。
まとめ
以上、クラスメイト向けに学校でしゃべらない子=場面緘黙児との接し方を説明しました。
めんどくさくてすみません。
でもこれが元場面緘黙の私の本音です。
私は幼稚園〜高校卒業まで、ずっと学校でしゃべりたかったけどしゃべれないままでした。
でももしクラスメイト全員がここに書いたように接してくれたらしゃべれるようになったんじゃないかなと思います。
まぁ全員は現実的じゃないとして、何人かだけでも。
ちなみにここに書いたのは高学年向けです。
高学年になると場面緘黙を治すことはかなり難しいんですけど、それでもここに書いたようなことをクラスメイトみんながやってくれたら治ると思います。
まぁ本人の治したい気持ち次第なところもありますけど。
ちなみに低学年や幼稚園児のクラスの子供に場面緘黙の気持ちを理解してもらうには「なっちゃんの声」という絵本を読むのがいいです。
関連ページ
- 学校でしゃべらない子の正体「場面緘黙症」とは何か?
- あなたの学校にまったくしゃべらない子っていませんでしたか? その子は場面緘黙症という病気だった可能性が高いです。 場面緘黙症とはどんな病気か、しゃべらない原因や治し方も解説します。
- 私が幼稚園から高校卒業までの15年間、学校でしゃべれなかった理由
- 私は場面緘黙症=学校でしゃべれない病気でした。 そのため幼稚園〜高校卒業までの15年間、学校でしゃべってません。 その間ほんとはしゃべりたくてしょうがなかったです。 なぜ私がしゃべりたいのにしゃべれなかったのか、自分なりに理由を分析してみたいと思います。
- 場面緘黙あるある
- 場面緘黙あるある、場面緘黙だと起こりがちなことを学校・外・家に分けてまとめました。
- 【先生向け】学校でしゃべらない子(=場面緘黙)への正しい接し方
- 子どもが学校でしゃべらない原因は色々ありますが、家ではしゃべれるのに学校でしゃべらない子は場面緘黙症という心の病気を持ってます。 今回は先生向けにこの学校でしゃべらない子(=場面緘黙)への正しい接し方を伝えます。
- 場面緘黙の子どもが保護者にしてほしいこと&治すために保護者にできること
- 場面緘黙の子どもに親としてどう接していいかわからない。 治すために親にできることはなんでもしたい。 今回はそんな場面緘黙の子どもを持って悩んでる保護者向けに場面緘黙の子が親にしてほしいこと・治すために親に協力できることを紹介します
- 【お願い】声が小さい人に声小さいと指摘するのはマジでやめてください
- 声が小さい人に声が小さいと指摘する。 これは絶対やってはいけないことです。 なぜなら、自信をなくして余計に声が小さくなるからです。 だから絶対やめてください。 声小さいと言われまくってきた私からのお願いです。