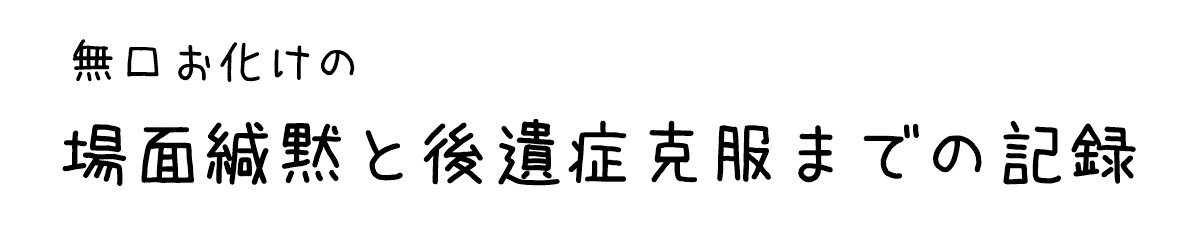場面緘黙の子どもが保護者にしてほしいこと&治すために保護者にできること
「場面緘黙の子どもに親としてどう接していいかわからない」
「治すために親にできることはなんでもしたい」
「早く治して普通にしゃべれる子にしてあげたい」

今回はそんな場面緘黙の子どもを持って悩んでる保護者向けに場面緘黙の子が親にしてほしいこと・治すために親に協力できることを紹介します。
場面緘黙の子供が保護者にしてほしいこと
まずは場面緘黙だった私が当時親にしてほしかったことを紹介します。
1. 家をリラックスして安心できる場所にすること
場面緘黙の子を持つ親が一番優先すべきなのは家をリラックスして安心できる場所にすることです。
場面緘黙の子にとって一番つらい場所が学校で、学校では緊張しっぱなしなので、せめて家ではリラックスできないと心が壊れてしまいます。
まぁ実際、場面緘黙のことを知らない親は子どもに
「なんでしゃべらないの?」
「友達できた?」
「学校楽しかった?」
などと聞いちゃう人が多いです。
そういう親に場面緘黙の子どもは心を閉ざします。
場面緘黙の子にとって自宅で一番必要なのは心の安らぎです。
だから家は学校であった嫌なことを全部忘れて、安心してリラックスできる場所にするのが理想です。
2. 否定しない。ありのままを受け入れる
場面緘黙の子どもは周りの人たちから否定されまくってます。
クラスメイトからは「しゃべらなきゃダメだよ」と言われ、
先生からは「なんでしゃべらないんだ!」「答えなさい!」と怒られ、
家でまで親に「あんた学校でしゃべらないんだって?なんでしゃべらないの?しゃべりなさいよ。」みたいに言われてしまうと居場所がなくなります。

まぁ場面緘黙のこと知らなかったら普通に言っちゃうと思いますけど…。
とにかく場面緘黙の子は日常的に周りから否定されてるのでセルフイメージがめっちゃ低くなります。
それにより単に学校でしゃべらないだけじゃなく、うつ病などの他の心の病気にもかかりやすくなり、不登校になっちゃう子も多いです。
そうならないよう、せめて親だけでも学校でしゃべらないからって子どもを否定せず、ありのままを受け入れてあげてください。
3. やりたいことはできるだけ自由にやらせてあげる
次にやりたいことはなるべく自由にやらせてあげてください。
学校でストレス溜まりまくってるのでそのストレスをゲームで発散してるならたとえやり過ぎだと思っても邪魔しないであげてください。
もしかしたら親に対して攻撃的になってストレスをぶつけてくる子もいるかもしれません。
そういう子にはゲームなど、何か別のストレス発散の仕方を教えてあげるといいです。
4. 習い事などは積極的にさせて学校以外の居場所を作ってあげる(※)
次にこれは高学年かつその子が学校以外の場所(床屋とか病院とか)ではしゃべれてる場合に有効な方法です。
高学年の場面緘黙の子が学校でしゃべれないのは緊張のせいではなく、しゃべらないキャラの固定化が原因です。
クラス中の子にしゃべれない子として認識されてる状態でしゃべり始めることはものすごく難しいのです。
一度こうなってしまうと、知り合いのいない学校に転校するか、進学するかしない限りなかなかしゃべり始めることができません。
でも転校や進学はそう簡単にできることじゃないですし、やれば必ずしゃべれるようになるとも限らずリスクがあります。
それよりもはるかに簡単でノーリスクでできることが、習い事です。
学校以外の場所でならしゃべれる子には積極的に習い事をやらせて(本人が望むなら)、学校以外でしゃべる経験を積ませておくと、進学したときなどにしゃべり始めやすくなります。
まぁ場面緘黙の子は人見知りもかなり激しいので習い事をしてもすぐにはしゃべれず友達もなかなかできないかもしれませんが、温かく見守りましょう。
ただし低学年の場合は学校以外の場所でもしゃべれない子もいるでしょう。
そういう子に習い事をさせても習い事先でもしゃべれず、単に学校以外にストレスのたまる場所を増やすだけになってしまう可能性があります。
ただあまりしゃべらなくてもできる運動とか音楽とか芸術とかであれば、子どもに自信をつけさせることもできるし低学年のうちから積極的にやらせてもいいと思います。
5. 学校でしゃべらないことには触れないでほしい
最後に学校でしゃべらないことに触れるのはできるだけやめてください。
子どもを普通にしゃべれるようにしてあげたい親の気持ちもわからなくはないですが、一番しゃべりたいのは子ども本人です。
そして場面緘黙の子どもは本当はしゃべりたいのにしゃべれず、悩みまくってます。
親子の信頼関係が厚いなら子どもの方から学校でしゃべれないことを相談してくるかもしれません。
そしたら全力で相談に乗ってあげてください。
でも子どもが何も言ってこないのに親の方から学校でしゃべらないことに触れるのはやめてあげてください。
ほとんどの子どもは家では普通にしゃべれるのに学校ではしゃべれない自分を情けなく思ってて、そのことを親に知られたくないですし、心配されるのも嫌です。
イジメられてることを親に言いたくないのと同じですね。
特に高学年の男の子にはプライドがあるので、これを言ってしまうとすぐに心を閉ざして親子関係がうまくいかなくなってしまうと思います。
ひどいと家でもしゃべれない全緘黙になってしまう子もいます。
※全緘黙=どこでも誰ともしゃべれない場面緘黙の究極形
あくまで親の役割は何も言わずに温かく見守ること。
それ以上のことは子どもに助けを求められるまではやらない方がいいです。
場面緘黙を治すために保護者にできること
親は見守るのが役目、といっても、場面緘黙を治すためにできることがあるなら出来る限りやってあげたいのが親の本音だと思います。
特に低学年のうちは、親にできることもいくつかあります。
低学年の場合
1. できるだけ家に友達を呼んで遊ばせる
まずは家で友達と遊ばせること。
子どもにとって一番安心できるのは家です。
なので学校ではしゃべれない友達とも家でならしゃべれることがあります。
そして家に呼ぶのは1人にして1:1で遊ばせるのがベストです。
始めはしゃべらなくても何度か遊んで慣れるとしゃべれると思います。
低学年なら親が入って3人で遊びつつ、時々親が話しかけることでしゃべり始めるきっかけになることもあります。
それが無理なら始めは親に耳打ちでささやき声でしゃべることから始めて慣れていくといいです。
また、同じクラスの子だとしゃべりにくい場合は違う学校の子とか別クラスの子ならしゃべれるかもしれません。
とにかく場面緘黙の子にとってリラックスできる家が一番しゃべり出しやすい場所なので、まずはここで家族以外の人としゃべる経験を積ませるといいです。
2. 親戚の家などに子供がいるなら積極的に交流して遊ばせる
次に親戚の家の子がいるならその子と遊ばせる。
始めはなるべく自宅にその子を招待して自宅で遊ばせましょう。
その方がリラックスできる分しゃべりやすいです。
それに慣れたら親戚の家にこちらから行き、向こうでもその子と2人で遊ばせてしゃべれるか試しましょう。
たぶん2人きりならしゃべれると思います。
もし万が一しゃべれなかったら一歩下がってまた自宅で遊んでもう少し慣れさせるといいです。
3. 先生に場面緘黙のことを伝えて理解してもらう
次に学校の先生に場面緘黙のことを伝えて理解してもらうこと。
ほとんどの場合、学校の先生は場面緘黙のことを知りません。
なので先生の中には場面緘黙の子に対して、不当な扱いをしてしまう人が多いです。
しゃべることを強要したり、しゃべらないことを甘えてるだけだと思って責めたり…。
本当はしゃべれるのにしゃべらない子は反抗的だと誤解されやすいですからね。
場面緘黙の子が学校を嫌になる原因が実は先生のせいってことも割とあると思います。
なので先生に場面緘黙がしゃべれるのに自分の意志でしゃべらないのではなく、しゃべりたくてもしゃべれない病気なんだということを伝えましょう。
かんもくネットに先生向けの資料があるので利用するといいです。
4. 先生に頼んで親子で放課後の教室などを使わせてもらい、学校でしゃべることに慣れさせる
最後に先生が場面緘黙のことを理解して協力してくれる場合にできるのがこの方法。
場面緘黙の子がしゃべり始めるには、スモールステップで少しずつしゃべれる人と場所を増やしていくことが大事です。
- 親と家でしゃべれる
- 親と学校でしゃべれる
- 家で先生としゃべれる
- 学校で先生としゃべれる
- 家で一番仲のいい友達としゃべれる
- 学校で一番仲のいい友達としゃべれる
という感じで。
普段しゃべれない学校ですでにしゃべれる人(=親)としゃべることで、学校でしゃべることに体を慣れさせておけば、他の人としゃべろうとしたときに感じる抵抗が少しマシになるはずです。
なのでもしできるなら時々親が学校に行って学校内、できれば教室内で子どもとしゃべる時間を取るといいです。
高学年の場合
小学校高学年以降の子どもはプライドが高くなってきて反抗期もあり、親のサポートを受けるのを嫌がる子が多いんじゃないかと思います。
なのである程度の年齢になったらサポートは学校に任せ、親は見守るだけにした方がいい、と個人的には思います。
もちろんそれは子どもによって違うと思うので、あくまで私が子供の時どうしてほしかったかでの意見です。
強いて言うなら、高学年以降になると学校以外ではしゃべれるようになる子が多いので、習い事などを積極的にやらせて学校以外にしゃべれる場所を作れると場面緘黙をだいぶ治しやすくなると思います。
これも親がやらせるんじゃなくて子どもの意志で選ばせることが大事なので、さりげなくパンフレットなどを子供の目の止まる場所に置いておいて、あとでやってみる?と聞くとか。
基本的に高学年までしゃべれなかった子は転校や進学などで自分がしゃべらないことを知ってる人がいない環境に行くまでなかなかしゃべれるようになりません。
しかしそこでしゃべれたとしても、長い間しゃべらずにいたことで他人とのコミュニケーションがうまくできず、場面緘黙の後遺症に苦しむことになりやすいです。
そうなるのをできるだけ防ぐため、進学や転校の前にまず習い事などでしゃべることに慣れておいた方がいいです。
またパソコンかスマホを買ってあげると掲示板やオンラインゲームなどで人と交流できて、孤独にならずに済むので積極的に買ってあげてほしいです。
まとめ
家では普通にしゃべるのに学校ではしゃべれない。
その特殊な性質から場面緘黙の子を持つ親は子どもにどう接していいのか戸惑うと思います。
ただ子ども本人からすると、特に特別なことはせず、普通の親が普通の子にやるのと同じように子供のありのままを受け入れてくれるのが一番いいです。
そして学校でしゃべった・しゃべらないの話題は家ではしないで欲しい。
家を安らげる場所にしてほしい。
それ以上のことはしなくていいから本当にそれだけは守って、って感じですね。
まぁ親子関係は人それぞれ全然違うので各家庭の状況で対応は変えるべきだと思いますが、家を安心して安らげる場所にすることだけは他のなによりも優先して欲しいと思います。
関連ページ
- 学校でしゃべらない子の正体「場面緘黙症」とは何か?
- あなたの学校にまったくしゃべらない子っていませんでしたか? その子は場面緘黙症という病気だった可能性が高いです。 場面緘黙症とはどんな病気か、しゃべらない原因や治し方も解説します。
- 私が幼稚園から高校卒業までの15年間、学校でしゃべれなかった理由
- 私は場面緘黙症=学校でしゃべれない病気でした。 そのため幼稚園〜高校卒業までの15年間、学校でしゃべってません。 その間ほんとはしゃべりたくてしょうがなかったです。 なぜ私がしゃべりたいのにしゃべれなかったのか、自分なりに理由を分析してみたいと思います。
- 場面緘黙あるある
- 場面緘黙あるある、場面緘黙だと起こりがちなことを学校・外・家に分けてまとめました。
- 【クラスメイト向け】学校でしゃべらない子(=場面緘黙)との接し方
- 場面緘黙症とは何かについてや、原因、治し方などを伝えるカテゴリーです。
- 【先生向け】学校でしゃべらない子(=場面緘黙)への正しい接し方
- 子どもが学校でしゃべらない原因は色々ありますが、家ではしゃべれるのに学校でしゃべらない子は場面緘黙症という心の病気を持ってます。 今回は先生向けにこの学校でしゃべらない子(=場面緘黙)への正しい接し方を伝えます。
- 【お願い】声が小さい人に声小さいと指摘するのはマジでやめてください
- 声が小さい人に声が小さいと指摘する。 これは絶対やってはいけないことです。 なぜなら、自信をなくして余計に声が小さくなるからです。 だから絶対やめてください。 声小さいと言われまくってきた私からのお願いです。