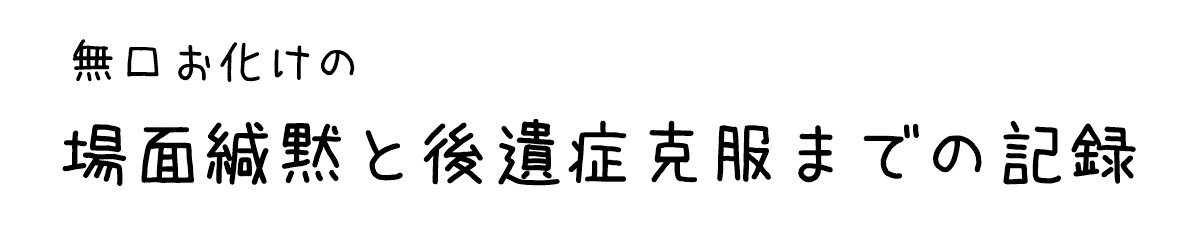【先生向け】学校でしゃべらない子(=場面緘黙)への正しい接し方

学校の先生なら一度は見たことがあるはずです。
学校でしゃべらない子。
しゃべらない原因は色々ありますが、家ではしゃべれるのに学校でしゃべらない子は場面緘黙症という心の病気を持ってます。
今回は先生向けにこの学校でしゃべらない子(=場面緘黙)への正しい接し方を伝えます。
場面緘黙児が先生に望むこと
1. 場面緘黙症について学び、しゃべらないのではなく「しゃべれない」と理解すること
まず場面緘黙症について学んで理解してほしいです。
しゃべらないのではなく、「しゃべれない」ということを。
そして本当はしゃべりたいのだということを。
ただの大人しい子・恥ずかしがり屋とは違うのだということ。
何も知らない先生からはしゃべれるのにしゃべらない生意気で反抗的な子だと思われてると思いますが、本当は
しゃべりたいのにしゃべれなくて困ってるかわいそうな子
なんです。
本当は友達とおしゃべりしたいのにしゃべれないから友達の輪に混ざれない。
それどころか、しゃべれるのにしゃべらないからみんなから誤解されて馬鹿にされたりイジメられたりしやすい。
場面緘黙症の子どもはほとんどの場合、先生からも親からもクラスメイトからも誰からも理解されず、たった一人で悩んでます。
本人は平気なように見えるかもしれませんが、実はめっちゃ寂しくてつらい想いをしてるんです。
それを理解してあげてください。理解してることをさりげなく伝えてください。
一人でも理解してくれてる人がいるだけで子供は相当心強いはずです。
2. しゃべるよう期待したり、プレッシャーをかけて話させようとしない
次に先生の中には場面緘黙の子供を頑張ってしゃべらせようとする人もいると思います。
場面緘黙のことを知ってるか知らないかにもよりますが、しゃべらない子がしゃべれるようになるよう助けてあげたい気持ちを持つことはめっちゃいいことです。
でもそのアプローチの仕方には気を付けてください。
場面緘黙の子供はしゃべるべき場面で極度の緊張状態になっていてしゃべれないのです。
場面緘黙の子が学校でしゃべろうとすると緊張します。
しゃべることを期待されたりプレッシャーを感じると余計に緊張が高まるため、そういうのは完全に逆効果になります。
場面緘黙の子がしゃべり始めるために大切なのは安心できてリラックスできる環境。
だから無理にしゃべらせようとしたり期待したりせず、
しゃべってもいいし、しゃべらなくてもいいし、準備ができたらしゃべればいいよ
というスタンスで温かく見守ってあげることが大事です。
3. 出欠を取るとき・授業で当てるときの対応について
次にしゃべらないといけない場面。
出欠を取るときや授業で当てるときにどうすべきか。
これは正直難しいです。
その子の状況によって柔軟に対応する必要があります。
私の場合、幼稚園〜小学校までは出欠のときも授業で当てられるときも完全にしゃべりませんでした。
中学ではそういうときだけしゃべり始めました。
なぜなら中学だと科目によって先生が違うので、担任以外の先生全員に私がしゃべらないことを理解してもらうのが不可能に近いことだったから。
というか怖い先生に当てられたときにしゃべらざるをえない雰囲気に押されてうっかりしゃべっちゃって、そこからしゃべるようになったんですけどね笑
それがいいか悪いかは人によると思いますが、私にとっては結果的によかったです。
でももちろんそれが裏目に出ることもあると思います。
怖い先生に容赦せずに返事するよう強要されてもしゃべれないままの人もいるでしょうし、その場合その怖い先生に怒られたことがトラウマになって授業に参加するのが怖くなり、学校に行けなくなる人もいるかもしれません。
なのでどっちがいいとも言えないです。
ただ強要しない場合、中学の学年担当の先生全員にその子が場面緘黙であることを理解してもらわなきゃいけないわけで、まずそれが可能かどうかですね。
無理ならどうしようもないです。
あとはその子と仲のいい子にその子がしゃべれないことを授業のたびにその子の代わりに先生に伝えてもらうか。
それも仲のいい子がいないとできないので難しいですしね。
まぁとにかく、小学校なら担任一人の問題なのでなんとかなりますが、中学以降は学年担当の先生全員に場面緘黙を理解してもらうことができるかできないかで対応が変わります。
で、できる場合は場面緘黙の子の状態によっては最初の授業のときに多少プレッシャーかけてしゃべらせてしまうのも一つの手。
最初から特別扱いしてしゃべる機会さえ与えないのもそれはそれでよくないと思います。
まずはその子がしゃべらないことを知らない体で他の生徒と同じように接してしゃべることを促し、しゃべるまで待つ。
10秒以上待ちながら様子を見て、行けそうなら声をかけて背中を押す、どうしてもしゃべれなそうにないなら諦める、という感じですね。
4. しゃべれないとできないことに気を遣い、フォローする(怒るのは論外)
次にその子がしゃべれないせいできないことを先生がしっかり把握し、フォローしてあげること。
しゃべれないと結構困るんですよね。
しゃべらないとできないことって色々あるので。
そして場面緘黙の子はしゃべれないから困ってても困ってるって言えないので誰にも助けを求められず、何もできません。
で、あとで先生に
「なんでやらなかったんだ!」
みたいに怒られる。
私はこれを学校生活で何度も何度も経験し、つらい思いをしてきました。
それはしゃべれないからできなかったんだよ
と言いたくても言えない。
せめて担任の先生にはわかってほしかったんですが、わかってくれない先生が多かったです。
具体的には
- 忘れ物したとき
- 授業中ペアワークのとき(特に英語・体育)
- 学校を休んだ日の授業でもらったものが必要になったとき
など
まぁ忘れものしたときが一番多かったです。
給食当番なのに白衣を忘れたから当番ができず、そのまま何もしなくて怒られるとかよくありました。
今思うとそういう困ったことがあったときは紙に書いて誰かに伝えればよかったなと思うんですが…。
そういう意味ではクラスの誰か、または何人かにその子の世話役をお願いしてその子が困ってる様子を見かけた時に助けてあげるよう言っておくのもありですね。
それでその子がクラスメイトの誰かを信頼するようになって困った時に紙に書いて自分の意志を伝えられるようになれば一番いいです。
場面緘黙の子はシャイの究極系なので紙に書いて伝えることすら最初はためらうかもしれませんが、その子も困るのは嫌なはずなのでちゃんと言い聞かせればやってくれるようになると思います。
ただし、紙に書いて伝えるってのができない場面もあるし、恥ずかしくてやりたくない場面も多少はあると思うので先生や周りの子がその子が困ってないか時々気にして、気づいてあげれるとよりいいですね。
ここまでが元場面緘黙の私が当時先生に最低限やってほしかったこと。
ここからは少しハードルは上がるかもしれないけどやってもらえるとより助かることを書きます。
その他場面緘黙児にやってあげるとベターなこと
1. しゃべる以外の部分でできるだけ褒めて自信をつけさせる
場面緘黙を治すためにとっても重要なのが自信を持つことです。
おそらくその子は場面緘黙のせいで自信を失ってます。
場面緘黙の子は「人としゃべる」という当たり前のことができないので自分は普通の人より劣ってると感じてセルフイメージが低くなりやすいからです。
ただでさえそれで自信をなくしてるのに周りの子たちからしゃべれないことでからかわれたり、場面緘黙に理解のない先生に怒られたりするなどしてさらに自信をなくしがちです。
このままだと絶対しゃべれません。
だからその子が自信を持てるように周りの環境を整えてあげることが大事。
そのためにまず先生にできることはその子をしゃべる以外の部分でできるだけ褒めてあげること。
たとえば
- 宿題を提出したとき
- テストでいい点を取ったとき
- 真面目に掃除してるとき
- 係の仕事をしたとき
- 何か人に親切をしたとき
など
ただし場面緘黙の子は感受性が豊かな分わざと褒めてるのとかはバレやすいので、あからさまな褒め方はやめた方がいいかも。
とりあえず1日1回目標で心から褒めれるようなことを探すといいと思います。
2. しゃべらなくてもできるクラスの係や役割を与えて自信をつけさせる(先生の手伝いなどでもいい)
自信をつけさせるには褒める以外にも方法があります。
それが何か役割を与えて責任感を持たせること。
しゃべらなくてもできる仕事はありますよね。
花の水やりとか、動物の世話とか、書類を運ぶのとか。
そういう役割を与えられると、自分も誰かの役に立ってると思えて自信が付く効果が多少あります。
しゃべらないと、いてもいなくても変わらないし、周りの人の評価が低いので自分は存在価値のない人間なんだと思いがち。
だから場面緘黙の子には積極的に役割を与えて自分の存在価値に気づかせてあげるといいです。
そしてそういう役割を果たしたら褒める理由も作れるのでそこで褒めたりお礼を言ったりすることで、二重の意味で自信を育てられます。
3. その子がいない日にクラスの生徒に場面緘黙の子の気持ちやしてはいけないことを教える
次にちょっとハードルが上がりますがその子がいない日を見計らってクラスの生徒に場面緘黙について教える時間を取る。
低学年なら
- 家では普通にしゃべれること
- 学校ではわざと話さないのではなく緊張してしゃべれなくなってしまうこと
- 本当は学校でもみんなとおしゃべりしたいのに、しゃべれなくてつらいこと
- 話しかけられると嬉しいのでいっぱい話しかけてほしいこと
- 「あって言ってみて」「なんでしゃべんないの?」「しゃべってよ」などと言われるとつらいこと
- みんなからやさしくされて、安心できるとしゃべれるようになるかもしれないこと
をその年齢の子がわかる言葉で伝えてください。
高学年なら
まず
- 家では普通に話せるのに学校では話せなくなる子どもが200人に1人くらいの割合でいて、Aさんがまさにそういう子なこと。
- Aさんが学校でしゃべろうとすると喉の筋肉が緊張してどうしても声が出せなくなること。つまり自分の意志ではどうしようもないこと。
- Aさんは本当はみんなとしゃべりたいのにしゃべれなくて毎日寂しくてつらい思いをしてること
を伝えて、
Aさんの気持ちを知りたい人は1日中学校でしゃべらないで生活したらどうなるか想像してみて。
想像したらわかると思うけどしゃべりたくてもしゃべれないのに
「あって言ってみて」
「なんでしゃべんないの?」
「しゃべってよ」
って言われるとつらいよね。
家ではしゃべれるAさんが学校でもしゃべれるようになるにはどうしたらいいと思う?
先生は学校がAさんにとって家みたいにリラックスして安心できる場所になればしゃべれると思うんだ。
だからAさんが安心できるように協力してあげてほしい。
Aさんはしゃべらなくてもうなづいたり首を振ったり、紙に書いたりでコミュニケーションは取れるよね。
だからしゃべらなくてもいいよ。ジェスチャーとかで答えてくれればいいよという感じでいっぱい話しかけてあげて。
毎日たくさん話しかけられるとAさんは嬉しくなるし、しゃべらなくてもいいとみんなが受け入れてくれると安心できる。
安心できる環境で嬉しくなると緊張しなくなってしゃべれるようになるかもしれない。
でも絶対にしゃべらせようとはしないで。しゃべるようにプレッシャーをかけられると緊張して余計にしゃべれなくなるから。
あくまでしゃべらなくてもいいよ。でもしゃべりたくなったらいつでもしゃべってね。って感じで接してあげて。
みんながそうやってAちゃんに接してればAちゃんは安心できてきっといつかしゃべり出すよ。
という感じなことを伝えてほしいです。
またはクラスの子たちにどうすればAちゃんがしゃべれるようになるか?というテーマで議論させるのもありですね。
4. その子を担当する先生全員に場面緘黙についての情報を共有
次に先生同士で場面緘黙についての情報を共有すること。
これは担任が全科目担当する小学校の先生ならそんなに頑張らなくていいことですが、科目によって先生が違う中学生以上の場合、重要になります。
ほとんどの先生は場面緘黙症のことを知りません。
だからしゃべれるのにしゃべらない反抗的な子だと勘違いしてしまうことが多いです。
それにより無意識に場面緘黙の子を傷つけてしまう先生がたくさんいます。
これを防ぐためにその子を担当する先生全員に場面緘黙についての情報を共有しておきたいです。
これはかんもくネットの配布資料が役に立ちます。
5. 席はなるべく不安の少ない目立たない席に
場面緘黙は不安障害です。
人から見られると緊張します。
特にしゃべってるところを見られることをとても恐れてます。
だから一番前などの目立つ席に配置されると緊張が高まり、場面緘黙の症状がひどくなってしまうことがあります。
できるならあまり目立たない席に配置してあげましょう。
その子が学校でリラックスできればできるほどしゃべれるようになる可能性が高まります。
6. なるべく大人しい子を近くに配置
場面緘黙の子どもは周りの子たちからしゃべらないことでからかわれやすいです。
また、自分から人に話しかけられない場面緘黙の子は友達ができにくく、孤立しやすいです。
しゃべりたくてもしゃべれないだけでもつらいのに、孤立していて、かついじめっ子にからかわれたり、いじめを受けたりしたら不登校になってしまう可能性があります。
そうならないよう、場面緘黙の子の近くにはなるべくその子と仲良くなれそうな大人しい子を配置し、よく他の子をからかういじめっ子タイプの子は離しましょう。
7. その子の場面緘黙の治療をサポートする
最後にこれは本当に余裕があってできる人にだけやってほしいことですが、場面緘黙の治療をサポートすること。
場面緘黙を自力で治すことはとっても難しいことです。というか不可能に近いことです。
それを可能にするのが周りの協力。
上記のことをして環境を整えることがまず最初の一歩。
それができたら次はその子がしゃべり始めるまでのサポートを積極的にします。
しかしこのサポートはその子からの信頼が得られてないとできません。
なのでまずはその子と仲良くなる必要があります。
そのためには普段から話しかけて非言語でもコミュニケーションを積極的に取ることが大事。
交換日記などを使うのも一つの方法です。
また年齢の低い子なら家庭訪問をして自宅でその子と遊ばせてもらうのもいい方法です。
高学年だと心を開くまでに時間がかかるので大変だと思いますが、常に「私はあなたの味方だよ」というメッセージを伝え続けていれば、いつか開いてくれるでしょう。
で、その子と仲良くなってきたら、時々その子がしゃべり始めやすい環境をセッティングしてその子と遊んだり、話したりして、その子があなたにしゃべってくれるのを待ちます。
場面緘黙の子がしゃべり始めやすい環境としては
- その子の自宅
- 学校の外(公園でもカフェでも)
- 学校内の個室
の順でしゃべり始めやすいです。
もちろんその際はしゃべるようプレッシャーをかけてはいけません。
ただ普通にしゃべらなくてもいいよスタンスで話しかけつつ、しゃべりたくなったらいつでもしゃべってねという感じで時々簡単に答えられる質問をしてみる、みたいな感じがいいです。
その子が先生のことを信頼していて、なおかつ十分にリラックスできていればいつか話し始めると思います。
で、もし話し始めたらここからスモールステップでその子が話せる「場所」を増やします。
その子の自宅で話せたなら次は公園で話してみる、公園で話せたら次は学校内の個室、という感じで少しずつハードルを上げて行きます。
学校の個室までいったら、次は個室のドアを開けた状態でしゃべれるか試す。
それもできたら次は他の先生もいる場所でも話せるか試す。
たとえば職員室。
最初は緊張してしゃべりにくいかもしれないのでまずは書類を運ぶのを手伝ってもらうなどで短時間だけ滞在する。
少し慣れたら職員室内で仕事を手伝ってもらうなどして少し長く滞在する。
で、時々小声で話しかけて答えるか様子を見る。
場面緘黙の子は自分がしゃべってるところを他の人に見られたリ、声を聞かれるのを恐れるので、最初はしゃべらないかもしれません。
しゃべらない場合は慣れるまでもう少し待つか、ハードルを下げます。
職員室だと人が多すぎてダメなら人が少ない時間帯を狙うとか、保健室に一緒に行くとか。
あるいは図書室で他の人には聞こえないささやき声で会話してみるとか。
そうやって最終的に人が多い職員室でもしゃべれるようになるまで頑張ってください。
それによりじっくり、しゃべってるところを人に見られたリ、声を聞かれることに慣れさせます。
それができたら次はしゃべれる「人」を増やします。
場面緘黙の子どもによって違うんですが、親しい人の方が話やすい場合、逆に知らない人の方が話しやすい場合があります。
その子にどっちの方が楽か聞いてみましょう。
で、親しい人ならクラスメイトの中で一番仲のいい子、知らない人ならその子が知らないけどあなたと仲のいい他の先生、またはお店の店員あたりが最適です。
で、3人で会う環境をセッティングしましょう。
クラスメイトの中で一番仲のいい子と3人の場合は、いきなり会話するんじゃなくて、遊びから入るのがおすすめです。
3人で遊びつつ、時々話しかける。最初はその子に言いたいことがあるときは耳打ちで先生にだけしゃべってもらうといいです。
で、遊んでるうちにその子が仲のいい子と話したくなって自分からしゃべり始めるのを待ちましょう。
その子が知らないけどあなたと仲のいい他の先生の場合は事前にその先生と打ち合わせをしておき、あなたとその子がしゃべってるところに偶然通りがかったふりをしてもらいます。
で、先生同士で挨拶して、ついでにその子のことを先生に紹介する。で、その先生にその子に何か簡単に答えられる質問をしてもらう。
で、しゃべるかどうか様子を見る、という感じですね。
またはその先生とあなたで何か仕事をして、その子にも手伝ってもらい、3人で共同作業する。
その間さりげなくその子に話しかけてその子がその先生の前でも普通にしゃべれる状態を作る。
その状態ができたらその先生からその子に話しかけてみてもらう、という感じ。
こっちの方がしゃべりやすそうですね。
こっちができてからさっき紹介して偶然通りがかかるパターンも試すといいかもしれません。
あとはお店の店員を利用するのもありです。
放課後でも土日でもその子と外で会う約束をし、ファミレスなどに行く。
で、店員さんに声を出して料理を注文する。
もちろん指をさすんじゃなくてちゃんと声を出すんだよと言い聞かせて。
最初にあなたが注文してお手本を見せてから注文させると上手くいきやすいと思います。
またはコンビニでコーヒーを買ってみる(サイズを言わなきゃいけない)とか、マックみたいなカウンターで注文する系の店でもいいですね。
で、これができたら次はあなたがいない場所でもその子がその人と話せるようにするといいです。
仲のいい子ならたぶんそのまま自然としゃべれるでしょう。
他の先生ならあなたがいないところで偶然通りがかったふりをして挨拶してもらう。
「こんにちは」は意外と難しくて言えないかもしれないので何か質問してもらうといいです。
店員ならコンビニで一人でコーヒーを買う、みたいな宿題を出すといいでしょう。
それができたらまた新しくしゃべれる人を増やしましょう。
1人から2人。2人から3人と。
3〜4人くらいになったら逆パターンをやるといいです。
仲のいい子が得意な子は知らない人、知らない人の方が得意な子は仲のいい子。
で、しゃべれる人がだんだん増えていくにつれ、その子が教室でしゃべり始めるハードルがどんどん下がってきます。
ある程度しゃべれる人が増えたら、または増える前からでも仲良くなったら、教室で時々その子に話しかけましょう。
始めは周りに聞こえないようにささやき声で話しかけ、その子も耳元でささやき声でならあなたに話せるようになるといいです。
その状態でしばらく先生とその子だけでこっそり会話する場面を増やし、教室でしゃべることに慣らしていきます。
ある程度慣れたら時々普通の声で話すようにする。
その子も思わず普通の声でしゃべっちゃうことを期待して。
しゃべっちゃえばラッキー、しゃべらなかったらまぁ仕方ない。
どちらにせよ、教室でしゃべることに慣れられればオッケー。
先生と話すことに慣れたらクラスで一番仲のいい子とも教室で話すことにチャレンジさせます。
できればその子と席を隣にしてあげるといいでしょう。
で、先生と仲のいい子。
教室でしゃべれる人が2人もいる状況が作れればその子が教室で他の子とも話し始めるのは時間の問題。
あとは待つだけ。
ここまでできただけでも成功したようなものです。
そしてある日突然その子が自分から他の子ともしゃべり出す、ってのが理想的な場面緘黙の治し方です。
まぁこれは根気のいることですし、相当献身的な気持ちがないとできないと思うのですべての場面緘黙児がいるクラスの先生にこれをやれとは思いません。
あくまであなたが本気でその子を助けてあげたいと思うならやってみてください。
ちなみに保護者の協力が得られるならもう少し簡単で、保護者に学校に来てもらい、学校(特に教室)でしゃべることに慣れさせるのも効果があります。
先生がその子と仲良くなるために自宅で遊ばせてもらうこともできますしね。
またクラスで仲のいい子をその子の自宅に招待してもらって、まずは自宅で友達としゃべれるようにする。
次にその学校でも教室以外の場所でならその友達を話せるようにする。
最後に教室でもその友達を話せるようにする。
というステップが踏めます。
友達を1人から2人、3人と増やして同じ方法を取るとより効果的です。
まとめ
以上、だいぶ長くなりましたが、場面緘黙児が先生に望むこととやってあげるとよりベターなことを紹介しました。
まぁほとんどの日本の先生は忙しくてここまでやる時間はないでしょう。
でも「場面緘黙児が先生に望むこと」の部分だけでもいいのでやってあげてほしいです。
この記事を読んでる人の中には、しゃべらない子を本気でなんとかしてあげたいと思ってる優しい先生もいるかなと思ったので詳しい方法まで書きました。
といっても先生一人でこれだけやるのは大変だと思いますし、無理のない範囲でやってくださいね。
関連ページ
- 学校でしゃべらない子の正体「場面緘黙症」とは何か?
- あなたの学校にまったくしゃべらない子っていませんでしたか? その子は場面緘黙症という病気だった可能性が高いです。 場面緘黙症とはどんな病気か、しゃべらない原因や治し方も解説します。
- 私が幼稚園から高校卒業までの15年間、学校でしゃべれなかった理由
- 私は場面緘黙症=学校でしゃべれない病気でした。 そのため幼稚園〜高校卒業までの15年間、学校でしゃべってません。 その間ほんとはしゃべりたくてしょうがなかったです。 なぜ私がしゃべりたいのにしゃべれなかったのか、自分なりに理由を分析してみたいと思います。
- 場面緘黙あるある
- 場面緘黙あるある、場面緘黙だと起こりがちなことを学校・外・家に分けてまとめました。
- 【クラスメイト向け】学校でしゃべらない子(=場面緘黙)との接し方
- 場面緘黙症とは何かについてや、原因、治し方などを伝えるカテゴリーです。
- 場面緘黙の子どもが保護者にしてほしいこと&治すために保護者にできること
- 場面緘黙の子どもに親としてどう接していいかわからない。 治すために親にできることはなんでもしたい。 今回はそんな場面緘黙の子どもを持って悩んでる保護者向けに場面緘黙の子が親にしてほしいこと・治すために親に協力できることを紹介します
- 【お願い】声が小さい人に声小さいと指摘するのはマジでやめてください
- 声が小さい人に声が小さいと指摘する。 これは絶対やってはいけないことです。 なぜなら、自信をなくして余計に声が小さくなるからです。 だから絶対やめてください。 声小さいと言われまくってきた私からのお願いです。